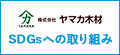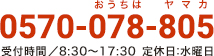2022.03.29 お役立ち情報
母子家庭でも持ち家はもてる?母子家庭の持ち家購入のメリットや注意点

母子家庭だと、「持ち家を買うより賃貸住宅に住み続けた方が良い」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、賃貸住宅だと家賃の支払いが半永久に続きますから、マイホームを購入した方が家計は楽になると思われる方は少なくないでしょう。
厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査結果(平成28年度)」によると、母子世帯の約15%が本人名義の持ち家に住んでいると回答しています。
シングルマザーでも、持ち家を購入して子育てに励んでいる方はたくさんいらっしゃるのです。
では、母子家庭で持ち家を購入することに、どんなメリットがあるのでしょうか。
また、どれくらいの年収があれば購入できるのでしょうか。
シングルマザーがマイホームを購入するときの注意点やポイントとあわせて紹介します。
出典:厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188155.pdf
目次
母子家庭で持ち家を購入するメリットとは?
いま賃貸に住んでいる母子家庭の方がマイホームを購入すると、どんなメリットがあるのでしょうか。享受できるメリットを、いくつか紹介しましょう。
家賃がかからない
持ち家を購入するメリットのひとつが、家賃がかからないこと。
毎月の家賃の支払いで生活費が足りないという方にとって、大きなメリットといえるでしょう。
住宅ローンを利用して持ち家を購入する場合、毎月の返済に追われることを心配されている方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、住宅ローンには完済があります。
完済後は住宅費の支出が大きく減るため、老後を安心して暮らせるというのも持ち家を購入するメリットです。
団体信用生命保険に加入できる
銀行などが提供する住宅ローンを契約するとき、「団体信用生命保険(団信)」への加入が求められます。
この保険は、契約者に万一のことがあってローンの返済ができなくなった場合、保険会社が残債をすべて支払ってくれるというものです。
この保険に加入していれば、仮に契約者である母親が亡くなったとしても、子どもにローンの支払いが引き継がれることはありません。
賃貸だと、そこに住み続ける限り家賃の支払いが続きますから、マイホームを購入した方が子どもへの負担も軽減できるのです。
なお、団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの返済額に含まれています。
また、最近の団体信用生命保険には女性専用の医療特約を付加できる商品も登場しています。
このため、現在加入している生命保険の見直しもでき、家計にゆとりが出ることも期待できるのです。
子どもに資産を残せる
子どもに資産を残せることも、持ち家を購入するメリットです。
賃貸だといくら家賃を支払っても自分のものにはなりませんが、持ち家だと住宅ローンを完済すれば完全に自分の所有物になります。
家庭事情の変化で住まなくなれば売却することも可能ですし、賃貸として貸し出せば家賃収益を得ることも可能です。
子どもが大きくなったときのことも考えて、住まい選びをすることも大切ではないでしょうか。
母子家庭でも住宅ローンを組んで持ち家を購入できる?
「母子家庭だと、住宅ローンの審査に通らないのでは?」と不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。
母子家庭でも、住宅ローンを利用できます。
「シングルマザーだから」「女性だから」という理由で、審査に通らないことはありません。
金融機関が重視するのは、あくまでも契約者の返済能力です。
一般的に、金融機関の審査では年齢や年収、健康状態、物件の担保評価などをチェックします。
これらの条件をクリアできれば、母子家庭でも住宅ローンを利用して持ち家を購入できるのです。
シングルマザーの方で注意したいのが「勤続年数」です。
安定した収入があることも、住宅ローンの審査では重視されますから、育休明けなどで働き始めて間もない方や転職を繰り返している方だと不利になることもあります。
また、契約社員や派遣社員のように短期間で異動になるような働き方も、審査に通るのが難しい場合があります。
逆に勤続年数が長ければ、パートなど非正規雇用の方でも利用できる住宅ローンはあります。
フラット35のように勤続年数を問わない住宅ローンもありますから、自分に適した商品をみつけてみましょう。
持ち家を購入するにはどれくらいの年収が必要?
住宅ローンの審査で重要な項目の一つが、年収です。
「年収いくら以上じゃなければ住宅ローンを契約できない」と公表している金融機関は少ないので、「自分の年収だと審査に通らないのでは?」と考えるシングルマザーの方は少なくないでしょう。
実は、返済可能な借入額であれば低年収でも利用できる住宅ローンはたくさんあります。
たとえば、フラット35であれば返済負担率が30%以内であれば年収100万円以下の方でも住宅ローンを利用できます。
フラット35以外でも、ネットバックでは100万円以上から利用できる商品もありますし、地方銀行や信用金庫だと200万円くらいでも相談にのってくれるところがあります。
金融機関が重視するのは、「年収に対する返済額の割合」です。
仮に年収が400万円あっても、その20倍に当たる8,000万円の住宅ローンを借り入れるのは難しいものです。
借入希望額が無理なく返済できる範囲であれば、年収が100~200万円くらいでも融資してくれる金融機関はたくさんあります。
では、どれくらいの借り入れができるのでしょうか。
一つの基準として、「返済負担率が25%以内」だと無理なく返済できる目安といわれます。
返済負担率とは、年収に対する年間のローン返済額の割合のことです。
年収200万円の方が年間50万円のローン返済をしている場合、返済負担率は25%(50万円÷200万円)になります。
ここで、いくらまで借り入れできるのかを年収別にシミュレーションしてみます。
シミュレーションに当たり、借入条件は以下の通りとします。
- 借入条件
・返済期間:35年(元利均等返済)
・金利:1.5%(全期間固定金利)
・返済負担率:25%
この条件で、年収別の借入可能額と毎月の返済額を試算した結果は以下の通りです。
| 年収 | 借入可能額 | 毎月の返済額 |
| 100万円 | 680万円 | 2万820円 |
| 150万円 | 1,020万円 | 3万1,230円 |
| 200万円 | 1,360万円 | 4万1,641円 |
| 250万円 | 1,701万円 | 5万2,081円 |
| 300万円 | 2,041万円 | 6万2,492円 |
| 350万円 | 2,381万円 | 7万2,902円 |
| 400万円 | 2,721万円 | 8万3,312円 |
参考:住宅保証機構「住宅ローンシミュレーション」
年収150万円でも、1,000万円以上の借り入れが可能ですし、300万円あれば2,000万円以上の借り入れも無理ではありません。
新築戸建住宅だと物件数は限られてきますが、中古やマンションなどにも広げることで持ち家の購入も夢ではないでしょう。
母子家庭で持ち家を購入する場合の注意点
シングルマザーの方が物件を探す際には、いくつか注意点があります。
以下の点を参考に、自らに適した物件を選びましょう。
子どもと長く過ごせる環境を選ぶ
家や土地を探すときのポイントとして「会社までの通勤時間」「保育園や学校までの距離」「スーパーや病院が近くにあるか」など、いくつかの条件があるでしょう。
こうした住環境が、ライフスタイルに適している地域で探すことがポイントの一つです。
たとえば、仕事を終えて家で食事の用意をされる方であれば、家から離れるほど子どもとの時間が取れなくなってしまいますから、できる限り職場の近くに住みたいものです。
また、帰りが遅い時間になるなら、総菜などを売っているスーパーが近いと便利です。
家庭の時間が取れる場所を重視しながら物件を選びましょう。
家庭環境が変わっても対応できる家づくりをする
長い人生では、何があるかわかりません。
いつか両親と同居することがあるかもしれませんし、再婚して新しい家族が生まれることだってあるでしょう。
持ち家だと、賃貸のように住み替えが容易ではありませんから、家族構成の変化に応じられる家づくりを考えることもポイントです。
たとえば、家族が増えても対応しやすい間取りの家づくりをする、売却しやすい資産性の高い土地に住むという点も考慮して物件を選びましょう。
ランニングコストがかかる
賃貸であれば、給湯器やエアコンなどが故障した場合、その修理代を含めオーナーがすべて対応してくれます。
また、固定資産税や建物の火災保険料などもオーナー負担です。
持ち家の場合は、これらの費用がすべて自己負担になります。住宅ローンの返済以外にもさまざまなランニングコストがかかりますし、長く住んでリフォームなどをする際の資金も必要になりますから、計画的に貯蓄をしておくことも重要なポイントです。
母子家庭で使える持ち家購入の補助金
家の購入に関して、国や自治体ではさまざまな支援制度を用意しています。
母子家庭の住宅購入支援に特化した制度で見ると、岐阜県には「母子父子寡婦福祉資金貸付金」が使えるでしょう。
この制度は修学資金がメインですが、住宅購入に関しては150万円、住宅移転については26万円が無利子で借りられます。
貸付後6ヵ月後から返済が始まりますが、住宅ローン以外にもこうした制度を利用することで、住まいの購入がしやすくなるでしょう。
また、母子家庭だけが対象ではありませんが、自治体によっては移住促進を目的とした住宅購入費などの助成制度を設けている自治体もあります。
家を購入する地域の自治体に確認してみましょう。
まとめ
母子家庭であっても住宅ローンを利用できますし、持ち家を購入することは可能です。
むしろ、賃貸で一生暮らすよりも住宅ローンを利用して持ち家を買った方が、トータルの住居費を抑えられるケースは多々あります。
また、団体信用生命保険に加入できたり、子どもに資産を残したりと、お子さんのことも考えた安心感も大きなメリットです。
家を買うのはハードルが高いと思われるかもしれませんが、シングルマザーでも十分に視野に入りますから検討してみてはいかがでしょうか。
QUOカードプレゼントキャンペーン実施中!
現在ヤマカ木材では、WEBでご予約いただいて来場されたお客様に最大で10,000円のQUOカードをプレゼントしています。
詳細はLINEよりお伝えしていますので、LINE友達登録後、ご確認くださいませ。