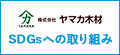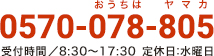2025.06.26 お役立ち情報
新築のシックハウス症候群はいつまで?原因となるホルムアルデヒドと対策

住宅には多くの建材が使われており、接着剤などには化学物質が含まれていることがあります。これらの化学物質やカビは、シックハウス症候群のリスクがあるので注意が必要です。
シックハウス症候群に一度かかると、なかなか完治できないといわれています。安全で快適に暮らせる家を手に入れるため、シックハウス症候群の原因や対策を知っておきましょう。
【この記事でわかること】
- シックハウス症候群とは?
- 新築住宅のシックハウス症候群はいつまで続くのか
- 新築住宅で生じるシックハウス症候群の主な原因
- 新築住宅で生じるホルムアルデヒドについて
- 新築住宅で生じるシックハウス症候群の対策
目次
シックハウス症候群とは?
シックハウス症候群は”病気の家の症候群”と直訳されるように、住宅に起因するさまざまな健康障害の総称です。
室内の汚染された空気を吸うことにより、さまざまな体調不良が発生し、原因となる住宅の外に出ると症状がなくなるか、または軽くなります。
家全体に新しい建材や設備がある新築の状態は、シックハウス症候群のリスクが最も高いタイミングです。そのほかにも、「壁紙を張り替えた」「床材を入れ替えた」「大型の家具を購入した」などの場合も、シックハウス症候群のリスクがあることを知っておきましょう。
シックハウス症候群にかかると、少しの化学物質にも反応してアレルギー症状を引き起こす”化学物質過敏症”を発症するリスクが高まります。
化学物質過敏症になると、日用品のちょっとした化学物質にも反応しやすくなってしまうため、発症する前に対策することが大切です。
シックハウス症候群の症状
新しい家に引っ越してから以下のような症状に心当たりのある人は、シックハウス症候群のおそれがあります。
- 鼻がよく詰まる
- 目がかゆい
- 初夏を迎えたのに花粉症に似た症状がなかなか治らない
厚生労働省の「室内空気質健康影響研究会」の報告(2004年2月)によると、シックハウス症候群の典型的な症状として次のようなものが挙げられています。
- 皮膚や目、のどなどの刺激症状(目のチカチカ・のどの痛みなど)
- 全身倦怠感、めまい、頭痛・頭重などの不定愁訴
目・鼻・口などの粘膜に現れる花粉症に似たアレルギー症状のほか、全身のだるさ・めまい・頭痛なども、シックハウス症候群で引き起こされます。
シックハウス症候群が生じる原因
山形大学医学部の見解によると、シックハウス症候群が多くなった背景として、以下の原因が挙げられています。
- 住宅建設や日常生活で化学物質が多用されるようになった
- 住宅建設が省エネルギ-設計で高気密になった
- 生活習慣によって、自然換気が不足する状態となった
近年、住宅の高気密化が進んでおり、建材や建築工法等が変化したため、室内空気中の化学物質の濃度が高くなることが原因で発症しやすくなると考えられています。
代表的な化学物質は、ホルムアルデヒド(接着剤)、トルエン・キシレン(塗料の溶剤)、の成分であるパラジクロロベンゼン(防虫剤)等です。
シックハウス症候群の疑いが発生した場合、症状に応じて病院を受診する必要があります。
新築住宅のシックハウス症候群はいつまで続くの?
新築住宅のシックハウス症候群は、建築から4年程度続くとされています。
新築から時間が経過するほどシックハウス症候群のリスクは軽減されるため、住宅を購入する際は築5年以上経過した物件を選ぶとよいでしょう。
5年を目安としている理由は、建築基準法の内装仕上げの基準です。この基準では、シックハウス症候群を引き起こす代表的な化学物質”ホルムアルデヒド”の発散が多い建材は、使用を禁止されています。
しかし、施工から5年経過していれば、ホルムアルデヒドの放散量は少ないとされ、使用を認められています。
シックハウス症候群が人に与える影響は個人差が大きく、使用する建材や室内の換気能力によってもホルムアルデヒドの放散量は異なります。そのため、同じ室内にいても症状の出ない人や、敏感に反応してしまう人がいるでしょう。
一概に、築5年以上経過していれば絶対安心できるわけではありません。敏感な体質の家族がいる場合は、慎重に物件選びをしてください。
新築住宅で生じるシックハウス症候群の主な原因
新築住宅でシックハウス症候群が発生する主な原因として、以下が挙げられます。
- 化学物質の影響
- カビやダニの影響
- 気密性が極端に高い家の影響
化学物質の影響
建材に含まれる化学物質は、シックハウス症候群を引き起こす最も代表的な要因です。
何枚かの板を貼り合わせて強度を高める構造用合板の接着剤や、素材の傷みを抑えて見た目を良くするための塗料、経年劣化を防ぐための防腐剤などには、さまざまな種類の化学物質が含まれています。
そのなかでも、シックハウス症候群の要因となる化学物質は、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒド、トルエン、キシレンなどです。
各物質の特性を下記の表にまとめました。
| 化学物質 | 物質の特性 |
| ホルムアルデヒド | ● 刺激臭のある無色の気体
● 殺菌や殺虫、防腐作用があり低価格である ● 接着剤や塗料、建材に使用されている |
| アセトアルデヒド | ● 無色の液体
● 合成樹脂、合成ゴムなどの原料として使用されている |
| トルエン | ● 無色の液体
● 塗料や医薬品、インキ溶剤及び洗浄剤などに使用されている |
| キシレン | ● 無色の液体
● 内装材などの施工用接着剤、塗料などに使用されている |
| エチルベンゼン | ● 無色の液体
● 洗浄剤、有機合成、溶剤、希釈剤などに使用されている |
| スチレン | ● 無色の液体
● ポリスチレン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、AS樹脂、合成樹脂塗料などに使用されている |
| パラジクロロベンゼン | ● 白色の固形物
● 衣類の防虫剤やトイレの芳香剤などに使用されている |
| テトラデカン | ● 無色の液体
● 灯油や塗料などの溶剤などに使用されている |
| クロルピリホス | ● 無色または白色の固形物
● 殺虫剤、防虫剤及び防蟻剤などに使用されている |
※2025年6月時点
特に、ホルムアルデヒドは発がん性も指摘されており、人体への悪影響が大きい物質とされています。
カビやダニの影響
カビやダニは湿気が多いところを好むため、湿気が溜まりやすく抜けにくい構造の建物では増えやすいといえます。
近年、高気密・高断熱住宅が増えました。気密性が高いことは、湿度が抜けにくいことでもあります。
壁の内部に湿気が溜まると壁内結露を引き起こし、カビが増えやすい環境となるため、気密性の高い住宅を建てるなら換気対策がされている住宅を選びましょう。
気密性が極端に高い家の影響
高気密・高断熱の住宅は外からの空気の出入りや熱の伝わりを減らせるため、外気温の影響を受けることなく室温を一定に保てます。そのため、冷暖房の効率が向上するなどの省エネ性能に優れており、光熱費を抑えられる点がメリットです。
一方、シックハウス症候群の原因となる化学物質やカビ、ダニが外へ逃げにくく、シックハウス症候群を発症しやすくなります。シックハウス症候群を抑えるため、こまめに換気するなどして、衛生管理に気をつけることが大切です。
新築住宅で生じるホルムアルデヒドについて
ここでは、シックハウス症候群を引き起こす代表的な化学物質である、ホルムアルデヒドについて解説します。
- ノンホルムアルデヒド・低ホルムアルデヒドとは
- ホルムアルデヒドによって生じる健康障害
ノンホルムアルデヒド・低ホルムアルデヒドとは
ノンホルムアルデヒドとは、ホルムアルデヒドをほとんど含まない、あるいは放散しない材料のことです。全身倦怠感やめまい、頭痛などの健康障害を引き起こしにくくなります。
ノンホルムアルデヒドといっても、少量のホルムアルデヒドが使われている場合があるので注意が必要です。新築住宅にノンホルムアルデヒドの材料が使用されている場合は、念のため詳しく確認することをおすすめします。
低ホルムアルデヒドとは、通常よりもホルムアルデヒドの含有量が少ない材料のことです。シックハウス症候群を引き起こすリスクをある程度抑えられる点がメリットといえます。
なお、化学的な処理や素材を用いずに建材や家具、インテリアを製作することはほとんど不可能であるため、低ホルムアルデヒドをノンホルムアルデヒドと呼ぶ場合もあります。
シックハウス症候群が心配な場合、材料によってはJISやJASが等級を定めているため、『低ホルムアルデヒド』や『F☆☆☆☆』と書かれた材料のものを選ぶとよいでしょう。
ホルムアルデヒドの発散量に応じた等級は、次の表のように定められています。最も等級の高い『F☆☆☆☆』は『エフフォースター』と読みます。
※2025年6月時点
※出典:建築基準法に基づくシックハウス対策(P8)|国土交通省
ホルムアルデヒド以外の化学物質に関しては、使用量に制限がありません。そのため、建築基準法の規制を守っている家であっても、シックハウス症候群になる可能性があります。
また、シックハウス症候群の原因物質は基本的に揮発性です。そのため、冬の間に入居した建物では、暖かくなってきてから発散量が急激に増え、シックハウス症候群となってしまうケースもよく見られます。
なお、無垢材や自然塗料はホルムアルデヒドを発散しないため、より安心を重視したい場合は内装材に自然素材を取り入れるとよいでしょう。
ホルムアルデヒドによって生じる健康障害
住宅や家具には、石油化学成分を含んだ建材や接着剤、塗料などが多く使用されています。そこから放散されるホルムアルデヒドが体内に入ることで、さまざまな健康障害を引き起こします。
突然、目元がチカチカしたり全身倦怠感が生じたりした場合は、ホルムアルデヒドを疑いましょう。また、のどに痛みが出たときや、水分を取ったのに乾きやすいときにも、ホルムアルデヒドが原因であるおそれがあります。
以下は、気中濃度ごとに人体への影響をまとめたものです。
| 気中濃度 | 影響 |
| 0.2ppm | ● 臭気を感じるが、すぐに慣れて感じなくなる |
| 0.5ppm | ● 臭気のために不快感が起こる |
| 1〜2ppm | ● 目への刺激や耳鳴り、吐き気などが始まる |
| 3ppm | ● 刺激による苦痛を覚える |
| 5〜10ppm | ● 目・鼻・のどに強い刺激
● 正常な呼吸ができなくなる場合もある |
| 10〜20ppm | ● 涙・せきがでる
● 5〜10分間で急性中毒を起こす場合もある |
気中濃度が濃いまま放置しておくと、シックハウス症候群になるおそれがあるため、違和感が出たらすぐに病院で診察を受けましょう。
新築住宅で生じるシックハウス症候群の対策
シックハウス症候群にかかってしまうと、室内から外へ出るなどの対処で症状を抑えることはできますが、完治は困難です。
また、化学物質にも反応してアレルギー症状を引き起こす”化学物質過敏症”を発症してしまうと、常に不快感がつきまとうことになります。
そのため、原因物質が溜まりにくい居住空間にしたり、空気清浄機を設置したりするなどして、症状改善のための家づくりをすることが重要です。
ここでは、新築住宅で生じるシックハウス症候群の対策を以下の4つ紹介します。
- こまめに換気する
- 空気清浄機を設置する
- 原因物質となる家具や生活用品を避ける
- 原因物質が溜まりにくい構造にする
こまめに換気する
シックハウス症候群の予防や改善のためには、こまめな換気が重要です。
昨今の住まいは、一戸建て、マンションともにアルミサッシ窓で気密性が非常に高くなっており、化学物質が溜まりやすい構造になっています。
共働き夫婦や単身者などで日中ほとんど家に人がいない場合、換気する時間を設けておらず、部屋が半日以上閉め切られている状態になっているケースが少なくありません。そうなると、帰宅したとき気中濃度が高くなってしまいます。
こうした室内状態を避けるためにも、換気扇をまわしたり窓を開けたりなどを習慣づけましょう。エアコンの設置で室内外の空気が入れ替わると考えている人もいますが、家庭用エアコンは室内の空気のみを循環する仕組みで、室外との空気のやりとりは行われません。
また、自分で定期的に換気することを忘れてしまう場合は、リフォームなどで24時間換気システムを導入することも1つの選択肢です。24時間換気システムを導入すれば、自動的に室内の空気が換気されるため、空調管理がしやすくなります。
カビやダニが発生しやすい湿気を対策できるため、検討してみてください。
なお、2003年の建築基準法改正により、すべての新築建物で24時間換気システムの設置が義務化されました。1時間あたり0.5回以上換気することが必要条件となっています。
24時間換気によって室内の空気中の化学物質を排出できるため、健康的な暮らしを実現できます。
空気清浄機を設置する
空気清浄機でシックハウス症候群を完全に対策することは困難ですが、補助的な役割を期待できます。家庭用空気清浄機はPM2.5 や菌、においのような粒子状物質を除去して、室内の空気を綺麗に保つ仕組みになっているからです。
しかし、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドなどのガス状物質の場合は、空気清浄機の効果をあまり期待できません。とはいえ、補助的な役割は期待できるでしょう。
空気清浄機には、フィルターを使用するタイプと静電気を使用するタイプ、イオンを使用するタイプの3種類があります。このうち、シックハウスの原因となる化学物質を減らす目的で利用するなら、フィルタータイプのものがベストです。
原因物質となる家具や生活用品を避ける
接着剤を使っていない無垢材や昔ながらの漆喰などには、化学物質が含まれていません。
化学物質の少ない建材を選べば、シックハウス症候群のリスクを減らせるでしょう。たとえば、自然素材は一般的な建材に比べて多少費用が必要ですが、健康には変えられません。
また、シックハウス症候群の原因になる化学物質は、建材だけでなく生活用品にも使用されています。たとえば、カーペットを敷いたままにしていると、湿気がこもってカビやダニが発生しやすくなります。カーペットを清潔に保てないのであれば、フローリングのままのほうがカビやダニの発生は少ないでしょう。
古い家具から化学物質が発生しているおそれがあるため、タンスやテーブルなどの家具は刺激臭がないものを選びましょう。
さらに、建築基準法の改正によって、建材にはホルムアルデヒドの拡散量に関するガイドラインが設けられました。そこには『F☆』といった表示がされており、『F☆☆☆☆』など星の数が多いほど安全です。
原因物質が溜まりにくい構造にする
高気密・高断熱住宅は室内温度を快適に保ちやすい構造ですが、換気という面では心配はあります。壁内結露や窓の結露を減らす工夫をしているなど、原因物質が溜まりにくい構造の建物を選びましょう。
家を建てる際にできる対策方法は、以下の3つです。
- 接着剤を減らす
- 床材に国産無垢材を使用する
- 内装仕上げには漆喰や塗り壁を採用する
シックハウス症候群の原因となる代表的な化学物質である”ホルムアルデヒド”は、接着剤として使用されているケースが多くあります。そのため、接着剤で繋いだ合板や木材のカケラを接着剤と混ぜて成形したものなど、接着剤の多い建材は避けましょう。
床材に使用される建材は海外から輸入されているケースがありますが、その際に防虫や防疫のために化学物質で消毒されていることがあります。
裸足で触れる床に化学物質が使用された建材を採用するのは、敏感な人にとって抵抗感があるでしょう。床材だけでも国産無垢材を使用するなど、部分的に対策を取る方法があります。
内装仕上げに接着剤を用いると、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどの化学物質を抱えることになります。有害物質を抑えた壁にするために、漆喰や塗り壁を採用することも有効です。リビングや寝室など滞在時間の長い部屋から導入を検討すると良いでしょう。
構造や建材については、しっかりとハウスメーカーに相談して選ぶことをおすすめします。
なお、ヤマカ木材の「ナチュリエ」では漆喰の壁をLDKに採用しています。室内の湿気を吸収・放湿してくれる“呼吸する壁”を実現するため、アレルギーをお持ちの方にもおすすめです。漆喰はカラーリングできるので、お好きな色にカスタマイズできます。
LDK以外は健康に配慮したクロスを使用しているため、体にやさしい家づくりが可能です。
新築住宅のシックハウス症候群に関するよくある質問
ここでは、新築住宅のシックハウス症候群に関するよくある質問を紹介します。
- シックハウス症候群による死亡例はある?
- シックハウス症候群になりやすい人の特徴は?
- シックハウス症候群をセルフチェックする方法は?
シックハウス症候群による死亡例はある?
シックハウス症候群による死亡例は海外で見られており、中国では屋内の空気汚染によって、年間220万人もの青少年が死亡していることが発表され、半数は5歳未満です。
中国は、石炭の大量消費と自動車販売数の増加で大気汚染が深刻化していますが、室内の空気汚染は屋外と比較しても10倍ほど高い場合が多いとされています。
シックハウス症候群の原因物質として、代表的なホルムアルデヒドやベンゼンなどが、汚染物質として含まれています。危険度の高いホルムアルデヒドに至っては、建材や家具に使用されているケースが多いようです。
厚生労働省によると、住居内の空気汚染によって2012年に全世界で430万人が死亡し、ほとんどが東アジアやアフリカの低中所得の国々と推定されています。
シックハウス症候群は、目がチカチカしたり、のどに痛みが生じたりするだけでなく、最悪の場合は死に至る病です。
中国では死亡した人の半数は5歳未満であると報告されていますが、家にいる時間が長い主婦や老人、乳幼児はシックハウス症候群の症状が出やすい傾向にあります。
シックハウス症候群の症状が出るかどうかは個人差がありますが、シックハウス症候群を発症しないためにも、室内で予防と対策をしましょう。
※参考1:中国、シックハウス症候群で年間220万人の青少年が死亡|AFPBB News
※参考2:科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)|厚生労働省
シックハウス症候群になりやすい人の特徴は?
前述のとおり、シックハウス症候群になりやすい人の特徴は、家にいる時間が長い主婦や高齢者、乳幼児などです。
また、全国の20〜70歳の男女4,996名を対象にした千葉大学による研究では、シックハウス症候群を発症しやすい人は次のような特徴を持つと発表されています。
- 女性
- 若者
- アレルギー既往歴がある人
- 喫煙歴のある人や受動喫煙・副流煙を吸い込んでいる人
- 床がカーペット敷き、ホコリを目にする部屋に居住している人
特に、室内でカーペットを使用している場合は、使用していない場合と比較して、シックハウス症候群を発症するリスクが1.48倍程度増える可能性があるとわかっています。
ほかにも、アレルギー既往歴のある人は、ない人に比べて1.41倍程度シックハウス症候群を発症していると示唆されています。
シックハウス症候群の原因となる化学物質は生活用品にさえ含まれているため、原因を完全に排除することは困難です。
また、アレルギー体質の人の感受性の強さによっても、症状が変わってきます。同じ部屋で過ごしていても症状が出る人と出ない人がいるのは、体内の毒素を溜める場所の大きさや代謝に個人差があるからです。
シックハウス症候群を発症しやすい人の特徴に該当しない場合でも、マイホームを持つ際は使用する建材や塗料、家具などに気をつけましょう。
※参考:「シックハウス症候群」経験しやすい人や環境の特徴を算出 生活スタイルを変えると予防できる可能性|国立大学法人千葉大学
シックハウス症候群をセルフチェックする方法は?
シックハウス症候群をセルフチェックする場合、症状が自分に当てはまるかどうかで確認できるので、この記事で紹介した症状と自分の症状を比べてみてください。
また、症状のほかにも生活スタイルからセルフチェックができます。以下は、岡山県が掲載しているチェックリストの一例です。
- 日頃から窓を開けて換気する習慣があるか
- 湯沸器やガスコンロなどを使用しているときは、換気扇を常時稼働しているか
- 設置されている換気システムは常に稼働しているか、または定期的に清掃をしているか
- 洗面所などの換気扇は、常に稼働するようにしているか
- 冷暖房時には、換気扇を稼働したり窓を開けたりして換気しているか
当てはまる項目が多いほど、室内に化学物質が溜まっている状態になるので注意が必要です。
※参考:シックハウス症候群を防ぐための自己点検チェックリスト(1)|岡山県
新築住宅で生じるシックハウス症候群は十分な対策が必要
建材などに含まれる化学物質やダニ、カビなどが原因で引き起こされるのが、シックハウス症候群です。これによって化学物質過敏症を発症してしまうと、化粧品や柔軟剤など日常生活のなかで使う製品にも過敏になってしまうおそれがあります。
新築の住宅は特にリスクが高いので、できるだけ自然素材を選ぶなどの工夫をしましょう。
家を建築する段階で、化学物質の放出量が少ない建材や設備を選ぶことが重要です。
普段の暮らしのなかでこまめに換気するなどの対策も大切です。二方向に窓を設けるなど、風の通り道を確保しやすい間取りもよいでしょう。
新しく購入する家具も、F☆☆☆☆(フォースター)表示のあるものや、無垢材などの自然素材を選ぶと安心です。
また、シックハウス症候群の原因や予防・対策方法がわかっていたとしても、マイホームを持つ際は不安になる人は少なくありません。実際、家に使用されている建材や塗料などにどのくらい化学物質が含まれているのかを個人で確認することは困難です。
安心して暮らせる家を探すには、信頼できる施工会社選びが欠かせません。
ヤマカ木材では、老舗材木店として自然素材にこだわった健康住宅を提案しています。小さなお子さんから高齢者の方まで安心して暮らせるマイホームを実現します。家づくりはもちろん、資金計画にお悩みの人もお気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。