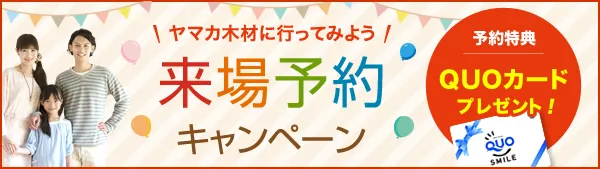2025.04.30 お役立ち情報
二人暮らしの生活費は平均いくらが目安?内訳をシミュレーションで解説

二人暮らしを検討している人の多くは、毎月の生活費に不安を抱いていることでしょう。
生活を豊かにするには、どの項目にいくらかかるのかを把握しなければなりません。
この記事では二人暮らしの平均生活費や節約するコツについて詳しく解説します。これから二人暮らしを開始する人は、ぜひ参考にしてください。
目次
二人暮らしの平均生活費・内訳
総務省が発表した『家計調査年報(家計収支編)2024年』によると、二人暮らしの平均支出は30万243円でした。食費は8万5,040円、水道光熱費は2万3,110円です。
ここでは、二人暮らしの平均生活費・内訳について、年齢ごとにさらに詳しく解説します。
- 20~30代の平均生活費
- 40~50代の平均生活費
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年(3-2 世帯主の年齢階級別)|総務省
20~30代の平均生活費
総務省の同調査によると、二人以上の世帯における20〜30代の平均生活費の内訳は以下の結果でした。
| 費目 | 平均費用 |
| 食料 | 7万2,099円 |
| 住居 | 3万1,426円 |
| 光熱・水道 | 1万8,474円 |
| 家具・家事用品 | 1万3,506円 |
| 被服及び履物 | 1万346円 |
| 保健医療 | 1万2,706円 |
| 交通・通信 | 4万3,814円 |
| 教育 | 3,853円 |
| 教養娯楽 | 2万7,364円 |
| その他の支出 | 3万8,026円 |
※34歳以下のケース
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年(3-2 世帯主の年齢階級別)|総務省
支出の中で大きな割合を占めたのは食費で、平均費用が7万2,099円でした。折半すると、一人当たり約3万6,000円かかっています。
次に多いのは交通・通信費の4万3,814円で、自動車等関係費が2万9,880円と多くを占めています。なお、教育費は3,853円とそれほどかかっていません。
40~50代の平均生活費
総務省の同調査によると、二人以上の世帯における40〜50代の平均生活費の内訳は以下のとおりです。
| 費目 | 平均費用(円) |
| 食料 | 9万2,762円 |
| 住居 | 1万7,420円 |
| 光熱・水道 | 2万2,950円 |
| 家具・家事用品 | 1万2,459円 |
| 被服及び履物 | 1万3,903円 |
| 保健医療 | 1万3,517円 |
| 交通・通信 | 5万1,162円 |
| 教育 | 3万4,542円 |
| 教養娯楽 | 3万5,800円 |
| その他の支出 | 5万5,189円 |
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年(3-2 世帯主の年齢階級別)|総務省
参照すると、40〜50代の平均生活費も20〜30代と同様、食料が9万2,762円と最も高い割合を占めました。次に多いのは20〜30代と同じく、交通・通信で5万1,162円です。
二人暮らしに必要な生活費の目安をシミュレーション
ここでは、二人暮らしに必要な生活費の目安を、就業形態別にシミュレーションします。
- 二人とも学生の場合
- 片働きの場合
- 共働きで二人とも正社員の場合
- 共働きで片方が非正規雇用の場合
二人とも学生の場合
二人とも学生の場合、生活費の目安は以下のとおりです。
| 収入 | 仕送り | 13万5,300円 |
| 奨学金 | 4万1,280円 | |
| アルバイト | 6万4,680円 | |
| 定職 | 980円 | |
| その他 | 6,360円 | |
| 合計 | 24万8,580円 | |
| 支出 | 食費 | 4万8,260円 |
| 住居費 | 5万3,020円 | |
| 交通費 | 8,420円 | |
| 教養娯楽費 | 2万6,540円 | |
| 書籍費 | 3,080円 | |
| 勉学費 | 2,860円 | |
| 日常費 | 1万4,860円 | |
| 電話代 | 6,920円 | |
| その他 | 4,340円 | |
| 貯金・繰越 | 2万5,940円 | |
| 合計 | 24万7,260円 |
※参考:ひとり暮らしの生活費 収支の合った楽しい生活|金融経済教育推進機構
※表はデータ元の数値を二人分として2倍の計算(住居費は除く)
金融経済教育推進機構のデータによると、二人暮らしの生活費は24万7,260円となっています。学生は仕送りを受けていますが、それだけでは不足しているため、アルバイトや奨学金で賄っていることがわかります。
片働きの場合
専業主婦世帯など、片働きの場合の生活費の目安は以下のとおりです。
| 収入 | 世帯主収入 | 49万9,173円 |
| 合計 | 49万9,173円 | |
| 支出 | 食料 | 8万6,326円 |
| 住居 | 2万291円 | |
| 光熱・水道 | 2万2,333円 | |
| 家具・家事用品 | 1万4,183円 | |
| 被服及び履物 | 1万513円 | |
| 保健医療 | 1万4,244円 | |
| 交通・通信 | 4万3,531円 | |
| 教育 | 1万3,685円 | |
| 教養娯楽 | 3万1,334円 | |
| その他の支出 | 5万4,603円 | |
| 合計 | 31万1,043円 |
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年|ファイル|統計データを探す|総務省
総務省の家計調査によると、専業主婦世帯の世帯主収入は49万9,173円で、支出合計は31万1,043円でした。
片働き世帯の食費は8万6,326円、交通・通信費は4万3,531円になっています。
共働きで二人とも正社員の場合
共働きで二人とも、正社員の場合の生活費の目安は以下のとおりです。
| 収入 | 世帯主収入 | 48万5,704円 |
| 世帯主の配偶者の収入 | 17万5,533円 | |
| 合計 | 66万1,237円 | |
| 支出 | 食料 | 9万1,348円 |
| 住居 | 1万7,850円 | |
| 光熱・水道 | 2万2,760円 | |
| 家具・家事用品 | 1万3,308円 | |
| 被服及び履物 | 1万2,783円 | |
| 保健医療 | 1万4,036円 | |
| 交通・通信 | 5万6,144円 | |
| 教育 | 2万3,005円 | |
| 教養娯楽 | 3万3,734円 | |
| その他の支出 | 6万795円 | |
| 合計 | 34万5,763円 |
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年|ファイル|統計データを探す|総務省
総務省の家計調査によると、共働き世帯の合計収入は66万1,237円で、支出合計は34万5,763円でした。全体的に、片働きより多い支出となっています。
共働きで片方が非正規雇用の場合
共働きで、片方が非正規雇用の場合の生活費の目安はこちらです。
| 収入 | 世帯主収入 | 52万3,891円 |
| 世帯主の配偶者の収入 | 5万6,545円 | |
| 合計 | 58万436円 | |
| 支出 | 食料 | 9万356円 |
| 住居 | 1万7,138円 | |
| 光熱・水道 | 2万2,680円 | |
| 家具・家事用品 | 1万3,283円 | |
| 被服及び履物 | 1万2,427円 | |
| 保健医療 | 1万4,127円 | |
| 交通・通信 | 5万8,608円 | |
| 教育 | 2万2,067円 | |
| 教養娯楽 | 3万3,643円 | |
| その他の支出 | 5万8,746円 | |
| 合計 | 34万3,075円 |
※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2024年|ファイル|統計データを探す|総務省
総務省の家計調査によると、共働きで片方が非正規雇用の場合の合計収入は58万436円で、支出合計は34万3,075円でした。
片方が非正規雇用の場合では片働きのケースより食費が多くなっています。
パートなどでどちらかの収入がある場合は、一人だけが働いている場合より家計にゆとりがあると見受けられます。
【内訳別】二人暮らしで生活費を節約するコツ
ここでは、二人暮らしで生活費を節約するコツを以下の内訳別に解説します。
- 家賃の節約術
- 水道光熱費の節約術
- 食費の節約術
- 通信費の節約術
- その他の節約術
家賃の節約術
家賃は、毎月の固定費の中でも大きな割合を占めるため、節約できるとより効果を得られます。家賃の節約術として、以下の方法が挙げられます。
- 家賃が低い物件に引っ越しをする
- 更新のタイミングで値下げ交渉をする
- 不要なオプションを解約する
現在の物件より家賃相場が低いエリアや、コンパクトな物件などに引っ越して家賃を抑える方法があります。
更新のタイミングで、築年数が経過していることを理由に値下げ交渉するのも良いでしょう。不動産会社が提供している不要なオプションサービスを解約するのも方法の1つです。
水道光熱費の節約術
水道・電気・ガスは生活するために毎日使用するため、節約を心がけて使うと無駄な出費を抑えられます。水道光熱費の主な節約術として、以下が挙げられます。
| 項目 | 節約術 |
| 水道 | ● 水を出しっぱなしにしない
● 節水シャワーヘッドに変える ● 食器はまとめて一度に洗う |
| 電気 | ● 家電の電源をこまめに切る
● エアコンの設定温度を室温に近づける ● 省エネ性能の高い家電に買い替える |
| ガス | ● お湯を沸かすときは給湯器のお湯を沸かす
● ガスコンロは中火で使用する ● 給湯温度を低めにする |
ガスはプロパンガスより都市ガスのほうが安い傾向にあるので、賃貸を選ぶ際は都市ガスの物件を選ぶとガス代を抑えられます。
食費の節約術
食費を節約するには、主に以下の方法が挙げられます。
- 節約効果の高い食材を選ぶ
- 余った食材は冷凍保存する
- 食材の在庫を整理整頓する
スーパーで特売になっている食材を選んでから、メニューを考えるのもおすすめです。
余った食材や料理は、冷凍保存するなど捨てることのないように活用しましょう。
冷蔵庫やパントリーの中が片付いていないと食材の使い忘れが多くなるため、常に整理整頓して中身を把握できるようにします。
通信費の節約術
通信費の節約術は以下のとおりです。
- 固定回線を見直す
- モバイル回線の乗り換え
- 端末購入方法の見直し
固定回線は、プロバイダーを変更すると通信費を削減できる可能性があります。スマホとインターネット回線をセットにすると、割引を受けることも可能です。
モバイル回線は、格安スマホの会社と契約すると通信費を減らせます。スマホの端末を安い機種にすると、毎月の通信料金への上乗せが少なく済むのでお得です。
その他の節約術
その他の節約術として、主に以下の方法が挙げられます。
| 項目 | 節約術 |
| 交通費 | ● 自転車や徒歩を活用する
● カーシェアリングの検討 ● エコドライブを心がける |
| 日用品・雑費 | ● 最安値のものを買う
● 特売品を購入する ● 繰り返して使えるものを活用する |
| 娯楽費 | ● 予算を決めて計画的に使う
● お金をかけずにレジャーなどを楽しむ ● レジャーの回数を減らす |
| 保険料 | ● 同じ保障額で保険料を安くする
● 無駄な保険を解約する |
節約は過剰に行うと心身にストレスを与えるので、適度な範囲内で支出を抑えるようにしましょう。
二人暮らしで生活費を分担する方法
二人暮らしで生活費を分担する場合は、二人の収入やライフスタイルなどを考慮して決めることが必要です。基本的な分担方法として、以下が挙げられます。
- 全額を一人で支払う
- 全額を折半して支払う
- 一人が固定費を多く支払う
- 固定費を二人で折半して支払う
全額を一人で支払う
全額を一人で支払う場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | ● 収入・支出の管理がしやすい
● 共働きの場合、どちらか一方の収入をまるごと貯蓄に回せる |
| デメリット | ● 片働きの場合、家計を負担している側の収入に大きく依存する
● 収入状況によっては実践できない場合がある |
共働きの場合は、家計を負担していない側の収入を全額貯蓄に回せるなどのメリットがあります。
一方、片働きの場合は家計を負担している側の収入に大きく依存することになるため、病気などで働けなくなると家計が行き詰まってしまうでしょう。
全額を折半して支払う
家計の全額を折半して支払う場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | ● 家計の収支を把握しやすい
● 余ったお金はお互い自由に使える ● 貯蓄を効率良くできる |
| デメリット | ● 収入に差があるとトラブルが発生しやすい
● お互いのお金の流れが不透明になる ● 収入や生活の変化に対応しにくい |
全額を折半して支払うケースでは、残ったお金を自分が自由に使える点がメリットです。ただし、お互いのお金の流れを掴みにくいのがデメリットといえます。
一人が固定費を多く支払う
家庭によっては、収入の多いほうが固定費を多く支払う場合もあります。一人が家計の固定費を多く支払う場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | ● 収入に差がある場合に公平感がある
● 収入が少ないほうの負担が軽くなる |
| デメリット | ● 負担する側の経済的なプレッシャーが大きい |
一人が固定費を多く支払う場合は、収入が少ないほうの負担が軽くなるので公平感があるのがメリットです。
一方、多く負担する側は支払う金額が増えるので、経済的なプレッシャーが大きくなってしまうでしょう。
固定費を二人で折半して支払う
固定費を二人で折半して支払う場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | ● 折半するので管理しやすい
● 収入が同程度の場合に公平感がある ● 無駄遣いを減らす意識が高まる |
| デメリット | ● 収入に差がある場合は不公平感がある
● どちらかが支払いを忘れるリスクがある |
住宅費や保険料などの固定費は毎月支払額が同じのため、折半して支払うときに管理がしやすいのがメリットです。収入が同程度の場合は公平感があります。
自分も固定費を負担するため、無駄遣いを減らす意識が高まるのも良い点です。
一方、収入に差がある場合に固定費を折半すると、収入が少ないほうが不公平に感じやすいでしょう。
また、どちらかが引き落とし口座への入金を怠ると決済されないため、未入金トラブルが発生するリスクもあります。
賃貸より持ち家のほうが家賃を抑えられるケースも
一般的に、長期間住む場合は賃貸より持ち家のほうが家賃を抑えられるケースもあります。
住宅ローンを利用して持ち家を購入すると、毎月ローン返済が必要になりますが、完済すれば固定資産税や維持管理費の支払いのみになります。完済すれば抵当権も外せるため、完全に自分の資産となり、子どもに財産として残せるでしょう。
一方、賃貸の場合は住んでいる限り家賃を毎月支払い続けなければならず、いくら払い込んでも自分の資産とはなりません。
住宅ローン控除の適用期間は所得税・住民税の還付を受けられるので、同じ金額の家賃を支払っている場合と比較すると、住宅ローンを利用しているほうが家計に残るお金を増やせるケースがあるでしょう。
長い目で見ると持ち家は老後の住まいに利用でき、高齢者でも安心して住み慣れた我が家で暮らせます。無理のない資金計画を立てて、持ち家を検討してみるのも選択肢の1つです。
家づくりを検討している人は、ヤマカ木材にお任せください。自然素材の家にこだわり、お客様に寄り添いながら最適なプランをご提案いたします。
二人暮らしの生活費は収入や費用内訳を考慮して設定しよう
二人の生活を豊かに安心して過ごすためには、収入だけでなく生活費の内訳をしっかりと考慮して設定することが必要です。
収入に見合った予算を立てることで、経済的に無理のない暮らしを手に入れられます。将来のプランも視野に入れながら、二人暮らしに最適な生活費の設定を検討してみてください。